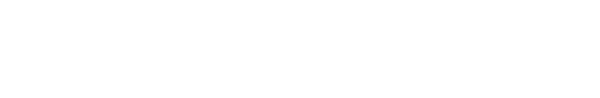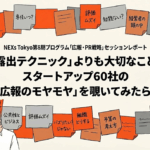“わかったつもり”の向こう側へ。50人の広報担当と挑んだ「他人の靴を履く」というメソッド

先日、とある公共セクターの広報担当者が全国から集まる研修会で、講師として登壇してきました。 テーマは「他人の靴を履く」。
会場には50名ほどが集まっていたんですが、ぶっちゃけ、冒頭の空気はかなり硬かった。 地域も業務領域もバラバラ、初対面同士が大半。「さて、何が始まるんだろう」という緊張感が、肌にピリピリ伝わってくるんですよね。
でも、この緊張感がほぐれていくプロセスこそが、広報の現場そのものだなとも思うんです。
今日は、そのワークショップで起きた「視点の転換」と、僕自身がこれまでのキャリアで痛感してきた「共感の正体」について、少し書いてみます。
■「他人の靴を履く」とは、とても深い技法
「他人の靴を履く」という言葉には、文化的な歴史があります。

「他人の靴を履く(Walk in someone’s shoes)」という言葉。 これ、単なる英語のイディオムだと思われがちですが、実はもっと深い、文化的な背景があるんですよね。
俳優の世界には、役作りのために、その人物が実際に履いていそうな靴を選び、その靴で街を歩いてみる。 英語には “walk in someone’s shoes” という表現があり、19世紀から共感や理解の比喩として使われてきました。また、哲学者ハンナ・アーレントは「他者の立場で考える力が、公共性をつくる」と言いました。
僕自身、中学生の頃は「私小説」を読み漁っていた文学少年だったんですが、あれもまさに「著者の靴を履いて、追体験する」行為だったなと。 そして、ちょっと飛躍しますが、広報という仕事は、心理学、演劇、哲学が重なる「人間理解のプロトタイピング」の上に成り立ってるんじゃないでしょうか。
「ターゲット分析」なんて無機質な言葉で片付けられがちですが、本質は「その人の痛みや喜びを、自分の肌感覚としてインストールできるか」に尽きます。
■熱中症予防を、女子高生の靴で歩いてみる
今回のワークでは、あえてベタな「熱中症予防の啓発ポスター作り」を題材にしました。 でも、ただのポスター作りではありません。チームごとに「誰の靴を履くか」を徹底的に縛ったんです。
- 高校生
- 高齢者
- 子どもの保護者
- 学校の先生
- 病院に通う方
など、かなり幅広い立場です。
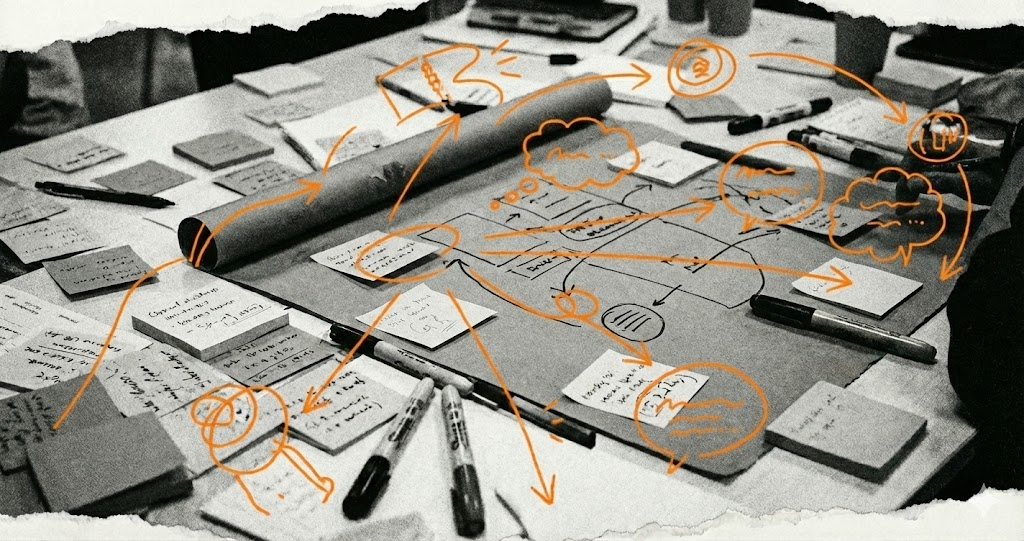
同じ「水筒を持とう」というメッセージでも、靴が変われば見える景色はガラリと変わります。
実際に出てきたアイデアが面白かった。 高校生担当チームからは、「健康とかどうでもいい。“荷物が増えてダサいのが嫌”というリアルな感情をどうハックするか?」という議論が出たり。 高齢者担当チームは、「水筒を持つことが“外出の自信”につながる」という文脈を見出したり。
この「視点のズレ」を面白がれるかどうかが、広報担当者の資質かもしれません。
■Sansan時代に痛感した「靴」のサイズ違い
少し僕の昔話を。 かつてSansanで「Eight」という名刺アプリを立ち上げていた頃の話です。
当時の僕は、どうしても「最先端のツールを使うITリテラシーの高い人」の靴ばかり履いて、メッセージを作ってしまっていた時期がありました。「クラウドで管理できれば便利でしょ?」と。 でも、実際に現場で名刺交換に困っているのは、ITに詳しくない営業マンだったり、紙のアナログな良さを大切にしている経営者だったりするわけです。

「自分の履き慣れた靴(IT業界の常識)」で歩いているうちは、絶対に届かない層がいる。 地方のコワーキングスペース行脚や、ITリテラシーの高くない方々向けの説明会を繰り返すうちに、それに気づいてからは、あえて自分とは遠い「地方の製造業の社長」や「新入社員」の憑依(ひょうい)を繰り返すようになりました。
今回のワークショップでも、経験の浅い参加者の方から 「知らない立場だと、つい自分の思い込みで創作してしまう癖に気づいた」 という感想をもらいました。そう、その「気づき」こそがスタートラインなんですよね。
■参加者の声──“深く考えることの大切さ”が腑に落ちた
事後にいただいたアンケート結果を見ると、いくつもの印象的な声が寄せられていました。
一部を匿名で紹介します。
「担当して日の浅い私にもとても分かりやすく、広報は“誰に何を伝えるのか”だと改めて実感しました。」
「講義を聞きながら、当院の広報はまだ改善できる部分が多いと気づきました。大変充実した研修でした。」
「グループワークが特に有意義でした。集合形式ならではの学びがあり、来てよかったと思いました。」
広報経験の長い方からは、
「相手の立場を考えるのは当然と思っていたけれど、ここまで深くやるとは…」
と驚きの声も。
視点の種類や深さによって、
刺さり方がこんなにも変わるのは、やはりワークの醍醐味ですね。
■広報活動に活かせそうな3つの示唆
今回のワークショップを通じて、改めて言語化したポイントを整理しておきます。公共セクターに限らず、スタートアップでも企業の広報でも全く同じです。
1:アウトプットを変える前に、視座を変える 響くコピーが書けない時は、文章力の問題ではありません。大抵は「靴」のサイズが合っていないだけ。視座が変われば、紡ぎ出される言葉は自然と変わります。
2:「わかったつもり」というノイズを消す データを見ただけで理解した気にならないこと。「その人は朝起きて最初に何を見るか?」まで想像できて初めて、靴を履いたと言えます。
3:媒体の制約は、クリエイティブの母 「ウチにはチラシしかない」「SNSが禁止されている」。そんな制約がある時こそ、企画の幅が試されます。媒体が限られていても、切り口(コンテキスト)は無限にありますから。
■運営目線での学び──“作り込みすぎない勇気”
また、運営の立場として、今回良い手ごたえを感じたのは、
“コンテンツを作り込みすぎず、場の温度に合わせて調整したこと” でした。

立場や経験が異なる50名に対して、
どこまで深く説明するか、どのタイミングでワークに移るか、
その場でアドリブで調整したのですが、
結果的にこれが非常にうまく働いたように思います。
広報もワークショップも、
“相手の反応を観察し、こちらの歩幅を合わせる”こと が本質なのだと、あらためて感じました。
■最後に──靴を履くことで、見える世界は変わる

広報は「情報を届ける」仕事ではなく、
「相手の世界を理解して橋をかける」仕事 ではないでしょうか。
自分の履き慣れた靴を脱ぐのは、ちょっと勇気がいります。裸足になるようで心許ない。 でも、一度他人の靴に足を入れて数歩歩いてみると、いつもの風景が驚くほど高い解像度で見えてくるはずです。
そしてその変化が、
メッセージを“伝える”から“伝わる”に変えていくのだと再認識したのでした!