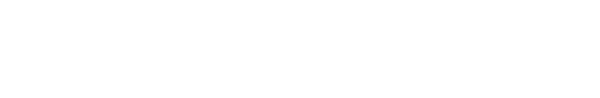共感は、エゴの先にある ——「エゴイスト」に学ぶ、“寄り添う広報”のつくりかた

米国では今、プライド月間のキャンペーン縮小が相次いでいます。
背景には、分断の深まる社会と、企業に対する政治的圧力。
そんな今だからこそ、映画『エゴイスト』に描かれた「共感」と「寄り添う姿勢」に、あらためて学ぶべきものがあると感じました。
“伝える”ことと“押しつける”ことの違い。
この映画をヒントに、広報にできることを考えてみます。
相手のために動いたつもりが、「ズレてたかも」と感じたことはありませんか?
その“ちょっとしたズレ”が、人間関係においても、広報活動においても、とても大きな意味を持つことがあります。
映画『エゴイスト』は、そんな「共感のすれ違い」に正面から向き合った作品。そこから、コミュニケーションに必要な“寄り添い方”のヒントを拾ってみました。
ネタバレにならない程度に、映画の趣旨を紹介します。主人公の浩輔は、苦しい状況に置かれている恋人・龍太のために「良かれと思って」ある行動をとります。でもそれは、龍太の気持ちや置かれている状況をちゃんと汲んだ上での行動ではありませんでした。
相手の生活や価値観、何より“その瞬間に必要としていたこと”をちゃんと見ようとしなかった。
その結果、望んでいなかった結果を生んでしまう。
この作品を観終えたとき、胸がチクリと痛みました。
「相手のため」と言いながら、どこかで“自分の満足”が先に立っていたこと、そしてそのことにうっすら気付いていながらも「これでよいならこれでいこう」と見てみぬふりをすることが、自分自身も何度もある気がして。
そしてこれって、広報の現場でもよく起きていることだなと思ったのです。
「伝える」より「触れる」広報へ
たとえば、CSRやSDGsの取り組みを「こんなことやってます!」と打ち出すコミュニケーション。それが独りよがりに聞こえてしまうときって、たいてい“伝えたい側の論理”だけで完結してるんですよね。
本当に大事なのは、受け手の文脈や背景に“触れる”姿勢。
どんな言葉で伝えるべきか?
それ以前に、そもそも今、このテーマを語るべきなのか?
そんな“大前提となる問い”をちゃんと持つことが、不可欠だと思うのです。
「ラベリング」は、共感の敵にもなる
映画『エゴイスト』の中で描かれる関係性は、「恋人」「家族」「支援者」といった言葉で括れないものばかり。
だからこそリアルで、心を打たれるんですよね。
広報でも同じです。
顧客、支援者、協力企業、地域住民、Z世代…
つい分かりやすさを求めてラベリングしてしまいがちですが、実際の関係性はもっと複雑であいまい。そして、ラベリングした関係でコミュニケーションを設計するのは楽だし、その定義をすることで安心してしまいがち。
でも、その「あいまいさ」や「中間性」をそのまま受け入れ、見せていくストーリーの方が、共感される時代になっているのでは?
「完璧」じゃなくていい。迷いながら、寄り添えばいい
浩輔が自分の未熟さに気づき、それを認め、龍太や家族と向き合い直していく姿には、「変わろうとする人の力強さ」がありました。
これも、コミュニケーションにおいて大きなヒントになります。
何かを発信するとき、つい「整った情報」や「成功事例」だけを届けたくなる。
でも今の社会では、「まだ途中なんです」「今こんなことで悩んでいます」という声の方が、はるかに響きます。
“弱さ”を見せることが、信頼のきっかけになる。
これまでの「守りの広報」ではなく、“共に歩む広報”への転換が求められているのだと思いました。
「寄り添う力」は、どこから始まるのか
映画『エゴイスト』は、相手に寄り添うことの難しさを静かに描いています。自分では「役に立ちたい」「支えたい」と思っても、それが空回りして距離を生むことがあります。つまり、相手の気持ちやタイミングを察するのは、驚くほど難しいのです。
だからこそ、本当に重要なのは――完璧を捨て、自分の弱さを隠さず、相手に向き合い続けること。自分の中にある戸惑いを受け止めた上で、それでも関係を築こうとするその姿勢は、言葉よりも伝わる強さがあります。
広報の現場も同じ。
一見うまく見えるメッセージより、
- 相手の声に耳を傾けようとする誠実さ
- 自らの不完全さをさらけ出す勇気
- そして、それでも前に進む素直さ
こうした要素が、真の共感と信頼につながるスタート地点なのではないでしょうか。と、作品を通じて思い返したのでした。